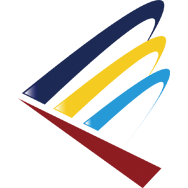八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
小倉の方より遺言書に関するご相談
2023年12月04日
亡くなった父の遺言書を母が預かっていました。この遺言書を開封する際は行政書士の先生に立ち会っていただくべきでしょうか?(小倉)
先日、小倉の自宅で同居していた父が亡くなりました。小倉の葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えなければと思っていたところ、母が父の遺言書を預かっているという話を始めました。父は相続について家族が揉めないようにとあらかじめ相続方法を考え、自筆で遺言書に記してくれたそうです。
遺言書は今はまだ自宅の金庫に保管してあるのですが、この遺言書は私たちで開封しても問題ないでしょうか?私や母が一人で勝手に開封してしまうと、中身を書き換えたと疑われそうで心配です。行政書士の先生立会いのもと開封できれば疑いの心配もなくなるのではないかと思うのですが、この遺言書はどのように開封すればいいでしょうか?
自宅保管の遺言書を開封するのは行政書士ではありません。家庭裁判所による検認を行いましょう。
今回亡くなったお父様が遺された遺言書は、遺言者本人が自筆で作成した「自筆証書遺言」だと思われます。自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、家庭裁判所に申立てを行い検認の手続きをとる必要があります。検認を行わずに自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料に処されることもありますので、検認は必ず行いましょう(ただし、2020年7月施行の法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用し遺言書を法務局で保管していた場合、検認は不要です)。
検認とは、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを明確にする手続きです。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としていますので、検認を行うことにより、ご相談者様が心配されていた他の相続人からの疑いも回避することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。すると家庭裁判所から検認の日の通知が届きます。申立人は必ず検認の日当日に家庭裁判所へ出向き検認に立ち会う必要がありますが、そのほかの相続人の立会いは任意のため相続人全員が揃う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がついていなければ財産の名義変更などの相続手続きを行うことができませんので、お早めに検認の申立ての準備に取りかかることをおすすめいたします。
八幡・中間相続遺言相談室は相続に特化した行政書士が、小倉の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。必要に応じて相続についての知識と経験が豊富な司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、小倉の皆様の相続手続きをワンストップでサポートいたしますので、小倉の相続ならどうぞ安心して八幡・中間相続遺言相談室へご依頼ください。初回のご相談は完全無料で承っております。
小倉の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
遺言書で寄付ができると聞きましたが、行政書士の先生詳しく教えてください。(小倉)
私は小倉在住の60代の主婦です。結婚歴はなく、生まれ育った小倉でずっと一人暮らしをしています。贅沢することもなく暮らしてきましたので、特に生活が苦しいということもはありません。財産としては若い時に蓄えた現金と小倉の両親から引き継いだ遺産が残っています。最近、私が亡くなったあとに私の財産を小倉の特定団体に寄付したいと思うようになりました。
もし寄付をしないと国の財産になると聞いたので、それなら小倉にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいのです。ただ、なにぶん死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安があります。寄付には遺言書が有効と聞きましたがもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。そちらの事務所にお伺いした方が良いですか?(小倉)
寄付をご検討されるのであれば公正証書遺言をおすすめします。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。ご相談者様のように寄付をお考えの場合は、②の公正証書遺言が最も確実な遺言書です。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証人に伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。さらに、遺言書の原本については公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。
なお、相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言内で遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定することをおすすめします。信頼できる人に遺言執行者の依頼をし、その方には公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。法律家に依頼することも可能です。
また、寄付先が決まったら、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくようにしましょう。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるため事前調査は必要です。
遺言書を活用することで、相続先を指定するだけでなく今回のように寄付などといったご相談者様ご自身の様々な意思を反映することが可能となります。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする八幡・中間相続遺言相談室の行政書士にお任せください。小倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている八幡・中間相続遺言相談室の専門家が、小倉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
小倉の方より遺言書に関するご相談
2023年05月08日
外出が出来ない主人が遺言書を作成する事は可能かどうか行政書士の先生教えていただけますか。(小倉)
私は小倉在住の60代の主婦です。70代の主人は過去の病の後遺症から半身不随で寝たきりです。意識はしっかりしているとは思いますが、もう年齢も年齢ですので、主人は子供たちのために遺言書を作成したいと言っています。私達には子供がふたりいますが、男の子同士だからかあまり仲が良くありません。主人は、亡くなった後にふたりが遺産分割で揉めるのではないかと危惧しています。遺産分割で子供同士がさらに仲たがいしてしまっては親として辛く、できれば避けたいものです。私も遺言書の作成には賛成ですが、なにぶん主人は障害があるため遺言書を作成しようにも他人が読めるような字を書くことは難しいように思います。主人でも遺言書を残せるような方法があれば教えていただきたいです。(小倉)
ご主人様が文字を書くことが難しいようであれば公正証書遺言での作成をお勧めします。
ご主人様が遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら公正証書遺言での作成をお勧めします。この遺言書は、遺言者の病床に公証人が出向いて作成のお手伝いをします。ただし作成時は二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整に多少のお時間を要することもあります。しかしながら公正証書遺言は作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の可能性がないだけでなく、開封時の検認手続きは不要です。
一方、ご主人様が文字を書くことが出来るようであれば自筆証書遺言という遺言書を作成することが可能です。この遺言書は特に費用をかけることなく遺言者の好きなタイミングで作成する事が出来ます。意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらいつでもお作り頂けます。また、この遺言書に添付する財産目録については、ご家族などといった身近な方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。なお、ご自宅で保管した場合、開封時には家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封する必要がありますが、法務局において保管した場合は検認は不要です。自筆証書遺言を作成する際は作成のルールを守り、法的に有効な形式で作成するようにしましょう。
公正証書遺言で作成する場合、お時間の調整がございますので、ご主人様が作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談して証人の依頼をすることをお勧めします。
八幡・中間相続遺言相談室では、小倉のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では小倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では小倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小倉の皆様、ならびに小倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。