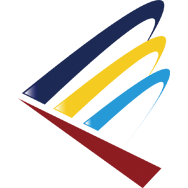八幡・中間相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
八幡の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
自身の財産を寄付したいのですが、遺言書に残せばいいのでしょうか。(八幡)
八幡にて会社を経営しているものです。長年仕事一筋で、暮らしてきました。結婚の話があがったこともありましたが、ご縁がなく、子供もおりません。最近気になっていることは、私にもしものことがあった場合の私の財産の行方です。私の両親はすでに亡くなっており、他に相続人にあたるのは兄の子供である甥です。甥にはもう何年もあっていませんので、彼に財産をゆずるつもりもありません。それよりも、八幡でお世話になってきた施設や団体などに寄付をするのがいいのではないかと考えています。寄付先はいくつか候補がありますが、確実に寄付をする時にはどのようにしたらいいのでしょうか。(八幡)
遺産の寄付を希望する場合には公正証書遺言を作成しましょう。
ご自身の意思を反映した遺言書を作成することで、どの財産を誰に遺すか決めることができます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回のように財産を特定の団体や施設に寄付をしたいと考えている場合、おすすめなのは公正証書遺言の作成です。
そもそも公正証書遺言とは、遺言を残す人(遺言者)が公証役場にて残したい内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文章を作成する遺言書です。公証人は法律の知識のある者ですので、方式に不備のない遺言書を確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、紛失や偽造などの心配はなく、自筆証書遺言には必要な検認手続きも必要ないため、すぐに手続きを進めることができます。
また、相続人以外の団体への寄付を考えている場合には、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は遺言書の内容に沿って必要な手続きを行う権利と義務を持ち、多くは遺言書で指名します。信用できる人に公正証書遺言を残しておくことを伝えておくと良いでしょう。
寄付先についてはまだいくつか候補があるということでしたが、団体によっては現金(または遺言執行者によって現金化した財産)のみ寄付を受けているところもあります。検討している団体にどのように受け付けているか、事前に確認しておきましょう。また、遺言書には寄付先の正式な団体名を記載することも大切です。
八幡・中間相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、八幡エリアの皆様をはじめ、八幡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
八幡・中間相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、八幡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。八幡・中間相続遺言相談室のスタッフ一同、八幡の皆様、ならびに八幡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
折尾の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
母の遺産相続の不動産分割方法で兄弟が揉めそうです。行政書士の先生にどうしたら良いかお尋ねしたい。(折尾)
はじめまして。先日逝去した母の遺産相続の遺産分割について、姉妹の中で揉め事につながる予感がしたため、知人からの紹介で初めて問合せをさせて頂きました。長い間、母は折尾に住んでおりまして、そこに実家とマンションを持っています。相続財産は不動産が主なもので、銀行口座には数百万の貯金があるだけでした。相続人は私と妹の二人ですが、正直に申し上げると決して仲が良いと言える姉妹関係ではありません。遺産分割協議での話し合いの際に衝突する事なく、穏便に公平な形で分けたいと考えているものの、現金と違って不動産をどうやって分けると公平なのかが分かりません。昔からの土地なので、なるべく不動産売却をせずに遺産分割できれば理想なのですが、それは難しいでしょうか。(折尾)
遺産相続での不動産分割方法について、いくつかの方法をご説明いたします。
八幡・中間相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
遺産相続における不動産の分割方法に悩まれているというお話でしたが、まずご確認いただきたい事が遺言書の有無です。もしも遺言書が遺されていたケースでは、遺産分割について話し合い(遺産分割協議)は行わず遺言書の内容に従って遺産分割を行う事になります。
今回は遺言書が無かったと仮定して、遺産相続のご説明をいたします。
被相続人が残した相続財産は相続人全員の共有財産であるめに、分割を行う必要があります。ご相談者さまが正に現在の状態がこれに当たります。姉妹2人の共有財産である遺産(メインが不動産)を分割し、遺産相続の手続きを行わなくてはなりません。なるべく不動産売却は行いたくないという意向でしたので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介します。
まずは「現物分割」というのは、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えばご相談者さまがご実家を引き継ぎ、妹様がマンションといった具合です。ただし、不動産評価が同じになる事は考えにくく、多くの場合に不公平が生じる事がありますが、相続人全員が承知をすればスムーズに遺産相続を行える方法です。
続いて「代償分割」です。これは相続人のうち一人もしくは何人かが被相続人の遺産を相続、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対しては不足分相当額の代償金や代償財産を支払うことによって分割する方法です。この場合は財産を相続した側が代償金として支払う額の金額を用意しなければならないという課題が発生しますが、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。
なお、不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法は「換価分割」と言います。
まず、ご相談者さまにはお母様のご実家とマンションの価値を調べる評価を行って頂いて、それからご姉妹での遺産分割については話し合いをされてはいかがでしょうか。
八幡・中間相続遺言相談室では遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きだけでなく相続全般に精通した専門家が皆様のお悩みにを丁寧にお伺いいたします。折尾にお住いの皆様、折尾で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、ご不明な点や不案内点があれば、ぜひお気軽に八幡・中間相続遺言相談室までお問合せください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
父の相続において、遺産分割協議書の作成が必要なのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(宗像)
宗像に住む50代主婦です。先日父が亡くなりました。父が住んでいた実家も宗像にあり、長女である私を含め兄弟も宗像の実家近くに住んでいます。父は長い間闘病していたのもあり、家族はある程度覚悟していたため、葬儀や遺産分割について父から話を聞いていました。葬儀を終えたあと相続人全員で父から聞いていた遺産分割について話合いをしました。父の財産は宗像の実家と預貯金が数百万のみです。遺言書は見つかりませんでしたが、父から分割内容について口頭で聞いていたため、相続人は全員納得しています。
相続人は家族のみで遺産分割についての話し合いもスムーズだったため遺産分割協議書を作成しなくても問題はなさそうです。このような相続でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。(宗像)
相続手続きで遺産分割協議書が必要なものもあり、今後のためにも作成した方が安心です。
遺言書がない場合の相続では、相続人全員の遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めます。遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。
遺産分割協議書は不動産の相続登記で必要なケースもありますが、相続では相続人同士の争いが起こりやすい状況でもあるため、今後の安心のためにも書面にまとめておくことをお勧めします。現時点では話し合いがスムーズだっとしても、今後争いが起こらないとは限りません。万が一揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意したことを再確認することができます。遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書が必要なケース(遺言書がない場合の遺産相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、すべての金融機関の用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士の争いを避けるため
相続は、突然財産が手に入る状況から、普段仲の良い関係であっても相続人同士でトラブルに発展してしまうことがあります。相続人同士のトラブル回避のためにも、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続に関するご相談を日々多くお伺いしております。宗像で相続手続きに関するご相談なら八幡・中間相続遺言相談室にお任せください。相続の専門家が宗像の皆様の相続を親身にサポートいたします。
宗像で相続のご相談なら八幡・中間相続遺言相談室の初回無料相談をお気軽にご利用ください。宗像の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
中間の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
寝たきりの主人が遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(中間)
自宅で寝たきりの主人についてご相談があります。私たち夫婦は中間で生まれ育ち結婚しました。主人は80代で、私は70代の主婦です。主人は以前病気をしてから現在はほぼ寝たきりで、日頃のお世話はヘルパーさんが来てくれています。意識はしっかりしていて、日にもよりますが受け答えもちゃんとできます。ただ、足腰の状態と年齢からもう歩くことはできないだろうといわれています。主人は小さいながらも会社経営をしていたため、亡くなった後のことが心配なようで、早く遺言書を作成したいと言っています。相続の際に子供達が揉めて、今後の事業に影響が出ることを心配しているようです。ただ、遺言書については誰も経験がないため、専門家に手伝ってもらう方が賢明とは思いますが、主人は上半身を上げることすらままならないので外出なんてもってのほかです。病床の主人は遺言書を書くことはできますか?(中間)
ご容態によって病床でも作成できる遺言書があります。
寝たきりでいらっしゃる方でもご容態によって作成できる遺言書があります。ご相談者様のご主人様は、意識がはっきりされているようですので、ご自身で遺言内容をお書きになれるようでしたら「自筆証書遺言」を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言方式は、その名の通り、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで完成する遺言書です。場所やタイミングを問いませんのですぐにでもお作りいただけるのと、費用がかからない点がおすすめポイントです。また、一緒に用意する財産目録に関しては、ご家族の方などがパソコン等で作成し預金通帳のコピーを添付することが許されています。ただし、ご主人が亡くなった後、開封の際の話になりますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
長い間寝たきりでいらして、文字を書くこと自体難しいようでしたら「公正証書遺言」という方式があります。こちらの遺言方式は、公証役場の公証人が病床に出向き、遺言者から遺言内容を聞き取って作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の正本、謄本を紛失しても再発行が可能です。また、自宅保管等の自筆証書遺言に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となるため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は、公証人のほかに二人以上の証人が立ち会う必要があります。その方々との日程調整に時間がかかる可能性がありますので、もしご主人様が作成を急がれる様でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしてください。
八幡・中間相続遺言相談室では、相続手続きについて中間の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が中間の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
中間の皆様、ならびに中間で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
宗像の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、離婚した妻は相続人になるのでしょうか。(宗像)
宗像に住む70代の者です。相続について伺いたくご連絡しました。
5年前より妻と2人で宗像の一軒家に暮らしていますが、実は妻とは籍を入れておらず、いわゆる内縁の妻となります。
私は30年前に前の妻と結婚し、10年前に離婚しました。しばらく1人で暮らしていましたが、その後今の内縁の妻と出会った次第です。
前の妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。
このような場合、私に将来何かあった時には前の妻にも私の財産は渡るのでしょうか。前妻とはもうまったく会う事もありませんので、私の財産を渡したくはありません。なにか対策をすることは出来るのでしょうか。(宗像)
離婚している前妻は相続人ではなく、財産が渡ることはありませんのでご安心ください。
ご相談いただき、ありがとうございます。
すでに離婚している前の妻は相続人にはあたりませんので、財産が渡ることはありません。
また、一緒にお住いの内縁の妻とは籍をいれていないということですので、この方も相続人にはあたらず、もしも、財産を渡したいというご意向がある場合には、生前のうちに対策する必要があります。
相続では遺言書の内容が優先されますので、遺言書で内縁の妻に財産を遺贈するという旨をより確実に残すことができる、公正証書遺言で作成しておくとよいでしょう。
また、もう一つの方法として特別縁故者に対しての財産分与制度があります。
これは法定相続人に該当する人がいない場合、財産の一部を内縁者のように生計を共にしていたり、特別に縁故のある人が受け取ることができる制度です。特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する際には、内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められると財産を受け取ることが可能となります。
なお、法定相続人は以下のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が亡くなっている時には、次の順位の人が法定相続人となります。
八幡・中間相続遺言相談室では、宗像のみならず、宗像周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。八幡・中間相続遺言相談室では宗像の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、八幡・中間相続遺言相談室では宗像の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
宗像の皆様、ならびに宗像で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。